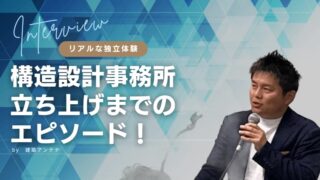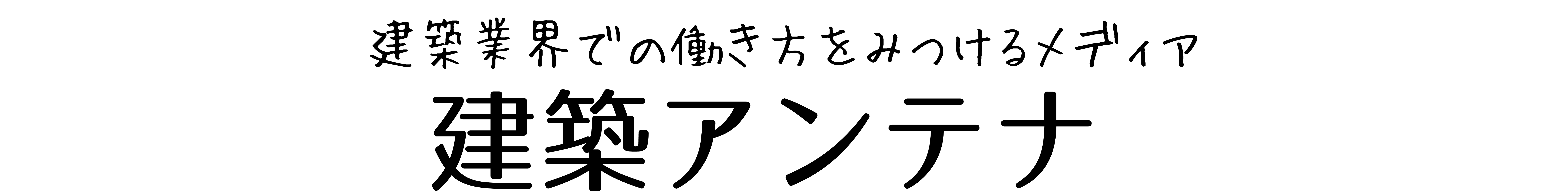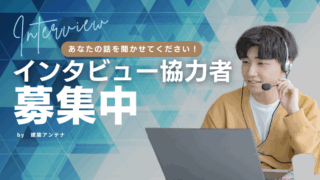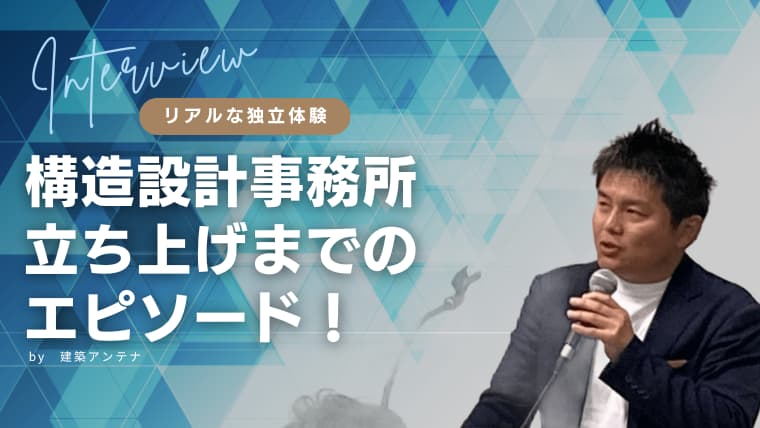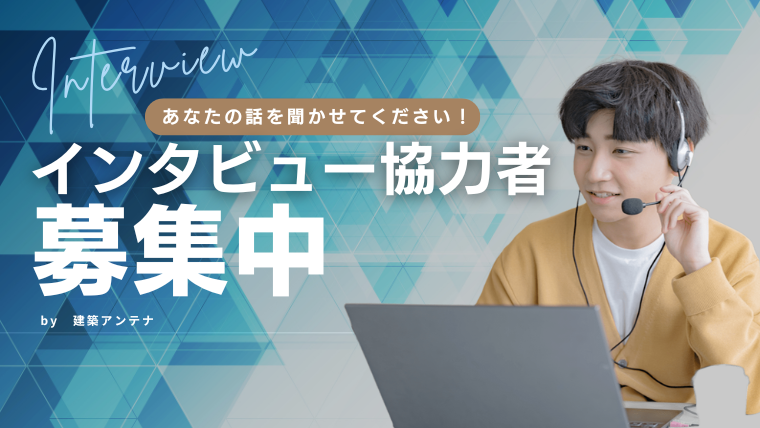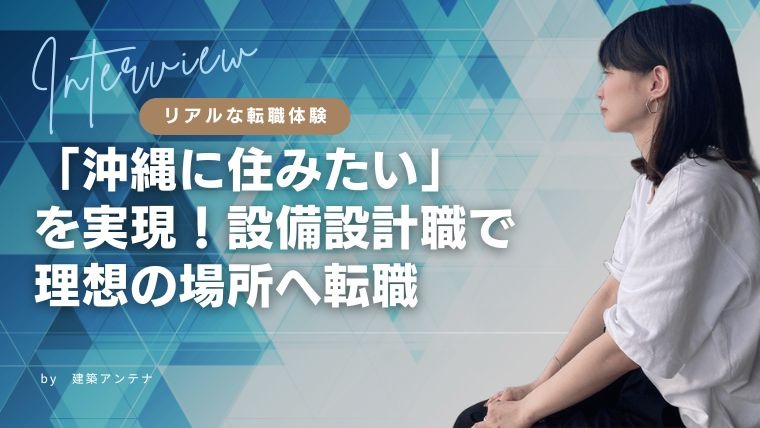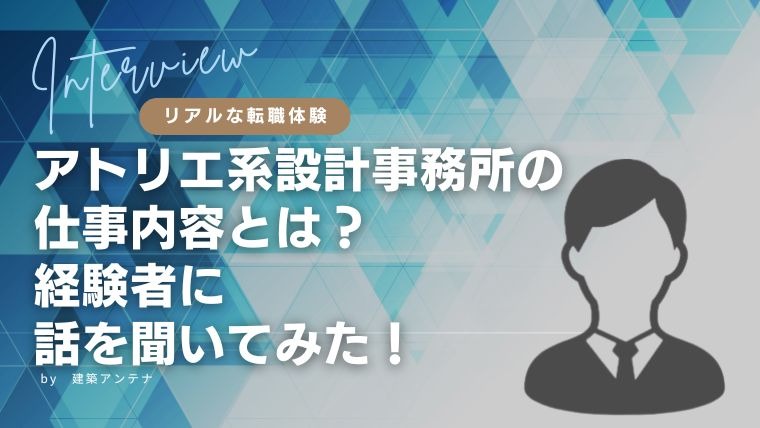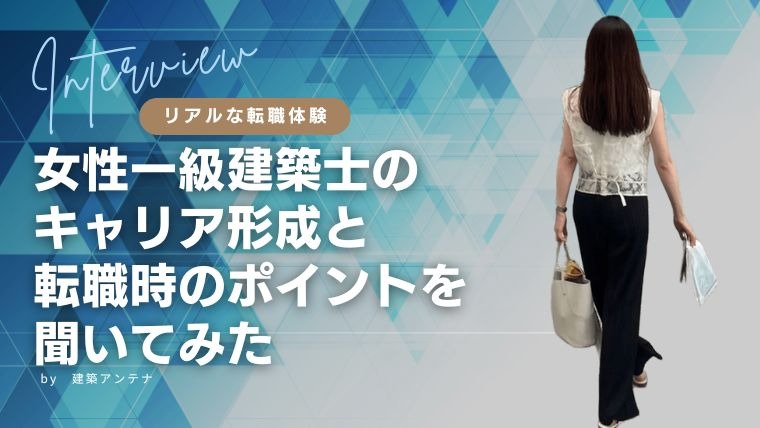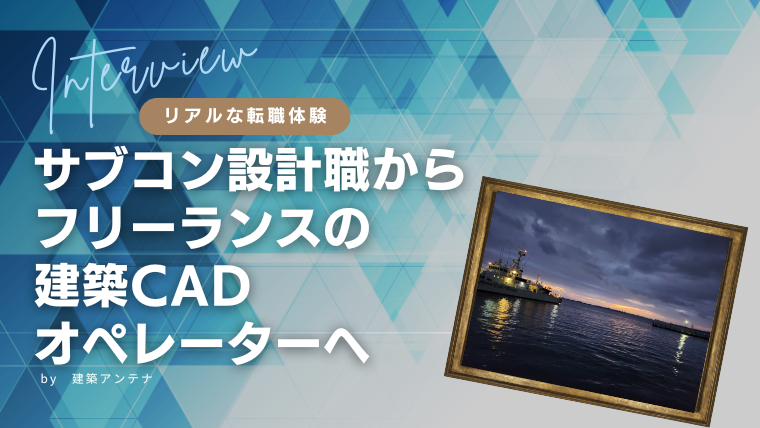【体験談】構造設計事務所がYouTubeで情報発信する理由を聞いてみた!
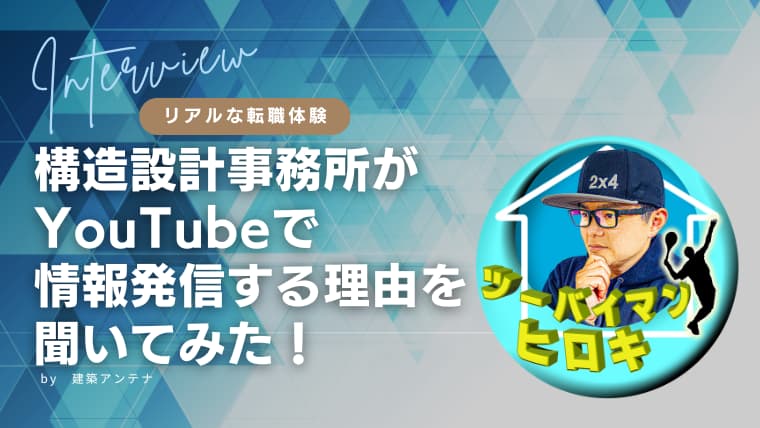

独立を考えているけど、SNSでの発信もしたほうがいいの?

YouTubeやInstagramって、何から始めればいいの?
最近は、建築の情報をSNSで情報発信を始める人も増えていますが、何から始めていいのかわからず、二の足を踏んでしまうという人は多いでしょう。
そんなときは、実際に独立しながら発信を続けている人の話を聞くのが一番参考になります!

そこで今回は、ツーバイフォー構造設計に特化した事務所を経営する傍ら、YouTubeやSNSでの発信も続けているヒロモクさんに話を伺いました。
ヒロモクさんプロフィール

ツーバイマン ヒロキ 戸鳴 宏樹
木造住宅の耐震性向上を目指し、「震災で倒壊する住宅ゼロ」を理念に掲げる構造設計事務所。ツーバイフォー工法を専門とする構造設計事務所 ヒロモクを2025年に設立。構造図・構造計算書の作成に加え、2×4工法に関する構造コンサルティングや勉強会を通じて、構造計画の重要性を積極的に発信している。
ヒロモクさんの発信はこちらから→https://1link.jp/2x4structure
話を聞いた人:建築CADオペ コハク(インタビュー実施時期:2025年8月)
YouTubeでツーバイフォー工法の情報発信を始めたきっかけ

——YouTubeでの発信を始めたきっかけを教えてください。
ヒロモクさん:3年前のコロナ禍の頃に、Web上に構造に関する情報をアップしておけば、出張が減るのではと思ったことがきっかけです。
その頃、北海道から沖縄まで全国で仕事をしていました。
僕の活動の拠点としている大阪で毎日感染者数が発表されている中、地方に行きづらくなったんです。
もちろん、現場に行かなければならない業務もありますが、構造の基本的な部分は動画を見てもらうだけで済むこともあります。
ツーバイフォー工法は在来木造工法と同様にオープン工法(誰でも建てられる)です。
もともと前職で社内向けの勉強会資料を作る側だったこともあり、その経験を活かして構造の知識を外に出していこうと考えたのが始まりです。
YouTubeがあれば『これ見といて』といった感じで使えるかなと。
——現在はYouTube以外にも複数のSNSを運営されていますね。
ヒロモクさん:YouTube、Instagram、Facebook、note、Threads(スレッズ)の他に、Discordでコミュニティも運営しています。
その中でも、建築業で仕事につなげるなら、情報収集のためにもFacebookはやっておいた方がいいです。
Facebookは、情報交換の質が全然違います。
X(旧Twitter)やTikTokと違って、Facebookは実名で登録するので、ある程度の倫理観や秩序が保たれた状態で横のつながりができ、実務者同士で技術の情報交換ができます。
SNSを敬遠する人もいますが、Facebookは実名で活動しているならではのネットワークを活用して、業界全体のボトムアップにもつなげられます。
若い子からしたら、おじさんくさいプラットフォームと思うかもしれませんが(笑)※1
建築の実務者にとっては必須のSNSだと思っています。
——「ツーバイマン ヒロキ」というキャラ設定がとても印象的です。「2×4」と書かれた黒いキャップやお名前の付け方も含め、ブランディングの見せ方がさすがだと感じます。
ヒロモクさん:ツーバイフォー工法で建てられている新築住宅は、全体の2割程度なので、明らかにマイノリティです。
ツーバイフォーを連想させる名前にしておけば『あいつツーバイフォーできるんちゃう』となると思ってつけました。
——SNS発信を始めてどんなメリットがありましたか?
ヒロモクさん:まず、ツーバイマン ヒロキという名前が、思っている以上に認知されていることです。
展示会でもセミナーでも初対面で『知ってますよ』と言ってもらえます。
例えば、僕のことを直接知らない人から名指しで連絡が来るようになったんです。
公開している情報で信憑性を担保できることで、実務にも自然と活かされているなと実感しています。
あとは各地域に私のことを知っている人がいて、地方で相談が来た時に私のことを紹介してくれるようになりました。
その時に、名刺代わりとしてのYouTubeやInstagram、Facebookがあると自分のことを知ってもらいたいときに楽ですよね。
自分から『信頼してほしい』とアピールしたわけじゃないですが、公開しているコンテンツが実務の信頼性の担保になっていると感じています。
YouTubeで木構造の情報を発信し続ける理由

——情報発信を継続していくための、モチベーションはどこから来ているのでしょうか?
ヒロモクさん:建築の人たちが皆、構造の勉強をしないからです。
——建築に携わる方にとっては、ハッとする言葉ですね。
ヒロモクさん:家が倒れたとしても、他人事のような顔をしている建築の人もいます。
なぜこんなことを言うかというと、僕の実家はまだ阪神大震災で傾いたままなんです。
地震が来たら、家は傾き、倒れることもあります。
能登半島地震も災害も自分は関係ないといった顔をしている人は多いですし、次の南海トラフ地震が来ると予想されていても、実際に行動する人は少ないのが現状です。
勉強すればするほど、構造計画が重要だと分かるんです。
僕たち建築の人間は命を守る仕事をしています。建築基準法にも『人の命と生活を守りなさい』と、一番はじめに書かれていますよね。
その義務を軽視する人をなくしたいという思いで、10年前から活動を続けています。
もちろん、大手ハウスメーカーは設計の段階で構造の検討や計算をしているので、しっかり考えられています。
ただ、実際には、大手ハウスメーカーで家を建てる人は少数派ですよね。
その他の多くの建築関係者が構造を学ぶために費用がかかるようでは、知識は広まりません。
だからこそ、僕のコンテンツや知識はすべて無料で公開しているんです。
もちろん、お金を稼がなければ生活はできません。そこで、まずは『種まき』として自分のコンテンツをインターネット上に置いてます。
本気で僕に依頼したい人はLINEから連絡してくれるので、そこで線引きをしています。
【建築基準法の第1条には、人の命を守るためにある法律だと定められている】
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
出典:建築基準法 第1条(e-Gov法令検索)
YouTubeの動画は、必要な人が必要な時に見てもらえれば

——YouTubeやSNSで発信している中で、大変だったことはありますか?
ヒロモクさん:口が悪いから、よそ行きの関西弁でしゃべらなあかん(笑)。というのは冗談で、大変なことはあまりないですね。
YouTubeはマネタイズ目的でやっていないから、再生回数にも執着していません。
もしマネタイズしていたら『やらなきゃいけない』『新しい動画出さなきゃ』となるけど、それがないので気持ち的に楽です。
YouTubeは、アルゴリズム的に定期的に同じ分野で動画を出し続けていくと、おすすめ動画として表示されるので、再生回数が増えて収益化につながる仕組みです。
僕の動画は、再生回数も1,000回、2,000回ほどあるものから、50回に満たないものまで、様々です。たまに出したらすごく再生されたりすることもあります。
ただ僕は『誰かがツーバイフォーの情報が必要になったタイミングで検索して、その時に必要な情報が載っていればいい』という感覚で動画を置いています。
——なるほど!私もCADの使い方を動画で検索して勉強した経験があります。実務の中でヒロモクさんの動画を見て学んだ人はきっと多いでしょうね。
建築設計ジャンルでこれから発信を始める人にアドバイス

——全く何も発信を始めていない状態だったら、何から始めるのがおすすめですか?
ヒロモクさん:それだったら、まずInstagramとnoteですね。
Instagramはビジュアルで訴求できるので、お施主さんへのアピールに効果的です。
特に意匠設計の人だったら、例えば毎日間取りを1個ずつ描いて投稿するだけでもいいと思います。
Instagramでは基本、文字は読まれないので、図面とかパースとか、見てわかるものが向いているんです。
noteは、普通のブログやホームページと違ってサーバー契約をする必要がありません。
アカウントを作るだけで始められるので簡単です。
普段考えたことや設計の話、勉強会に行ったことなどをnoteに何かしら残していけば、それが自分のコンテンツになっていきます。
ホームページを作らなくても、自分の情報をきちんと見せられる場所になるので、Instagramと並行してnoteもやるといいですよ。
——情報発信以外で、独立への準備としてやっておいたほうがいいことはありますか?
ヒロモクさん:独立は、辞める前からの準備が結構重要です。種まきは絶対やったほうがいいと思います。
また、自社の工法だけではなく、他の情報も積極的に取りに行くことが大切だと思います。
例えば『水しか知らなかったら、スポーツ飲料の良さも伝えられへんで』という話です。
『水が一番』と勧めるときにも、本当に水の良さを理解しているのか、それとも他を知らないから水を勧めているのかでは全く違います。
スポーツ飲料も飲んだうえで『やっぱり水が好き』と言えるなら、自信を持って水を勧められますよね。
もし、自社の商品しか知らずに、お客さんがスポーツ飲料に興味を持ったときに『スポーツ飲料は良くないよ』と否定してしまうようでは、ただのポジショントークやんと感じてしまいます。
他の構造の知識を得ていけば自分の視野も広がるし、noteなどで発信するネタにも困りません。
——なるほどです。ヒロモクさんも、ツーバイフォーを主軸としながらも、在来木造や鉄骨造やRC造なども学ばれているんですね。
ヒロモクさん:僕の事務所には在来木造の書籍もたくさんありますし、在来木造をやっている知り合いも多いですね。
——幅広い構法の知識を身につけておくことで、自分の専門性にも厚みが出るんですね。本日はすごくためになるお話をありがとうございました。
まとめ

ヒロモクさんのお話から、情報発信は信頼の土台づくりになると感じました。
無料で構造の知識を広める姿勢や、Facebookを活用した実務者同士の交流など、業界全体の知識を底上げしたいという思いが伝わってきます。
ヒロモクさんのお話を聞いて、私もブログの発信を通じて、誰かの役に立てるといいなと改めて感じました。
——ヒロモクさんには、これまでのキャリアや独立までの経緯についてもお話を伺いました。詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。